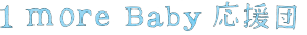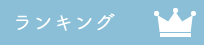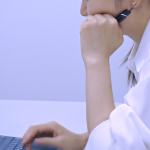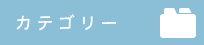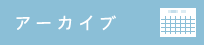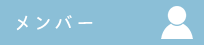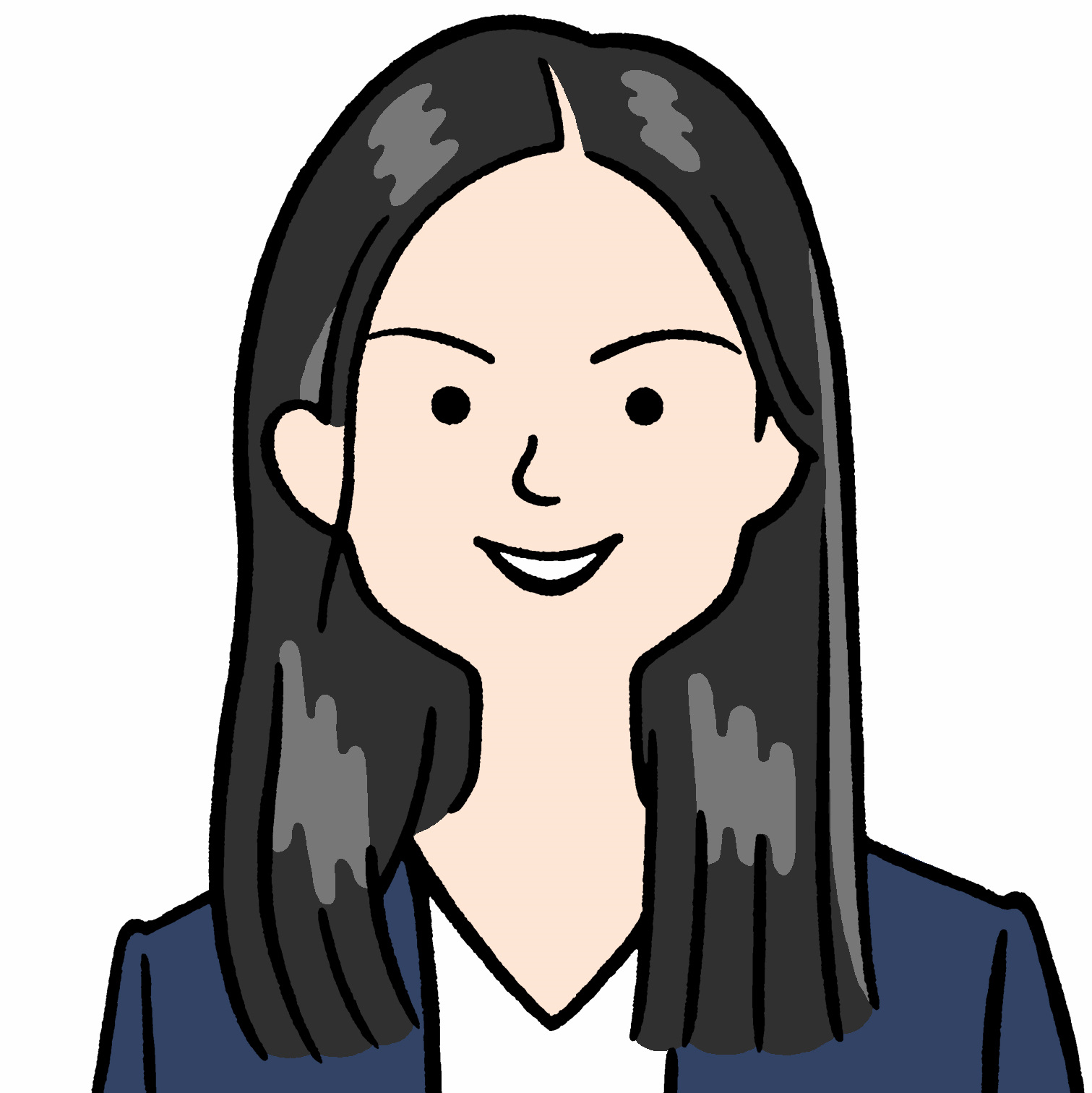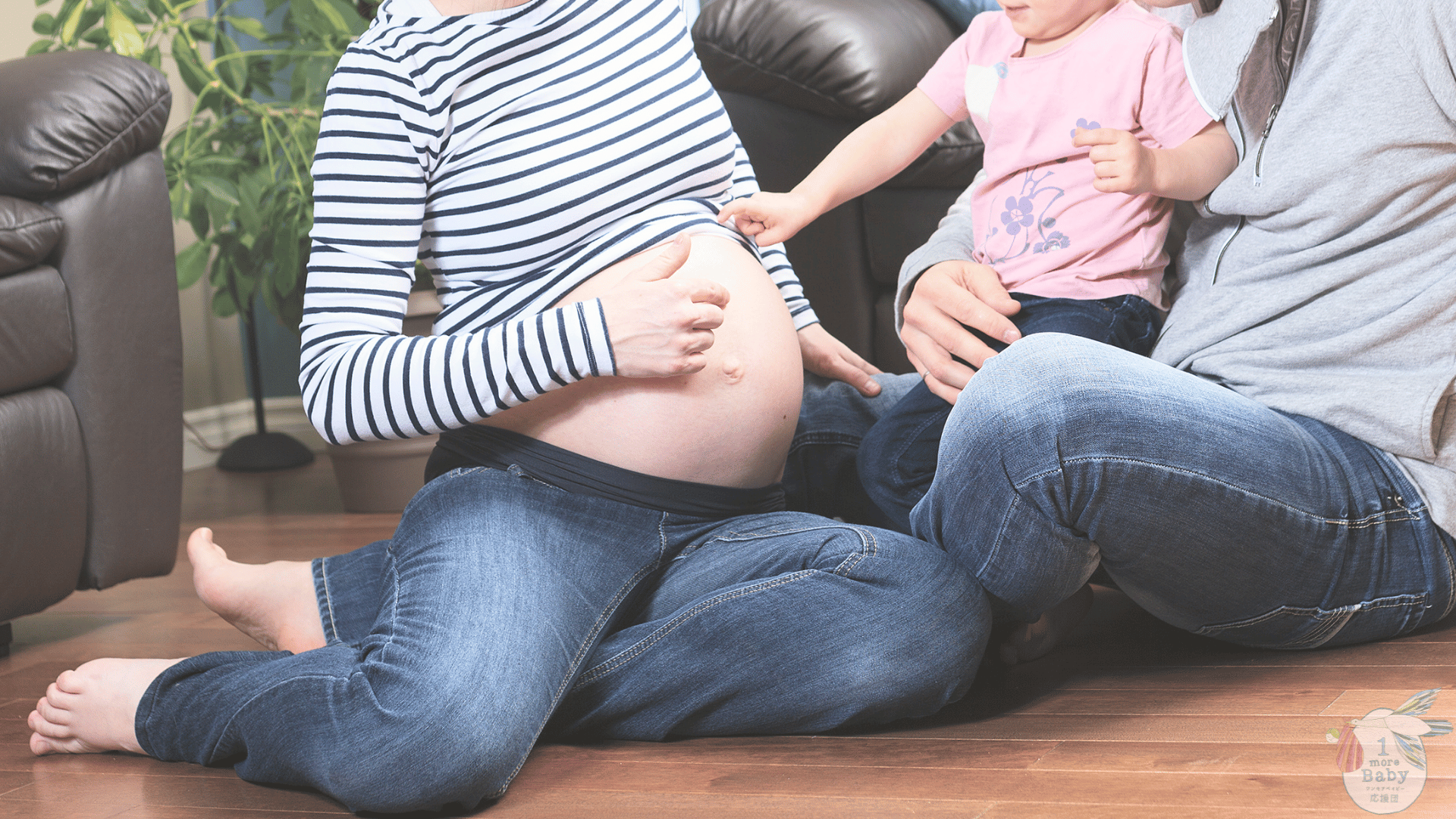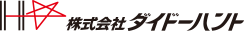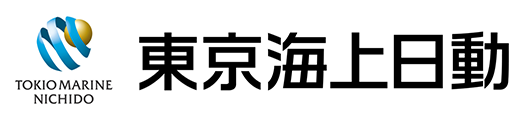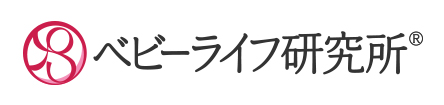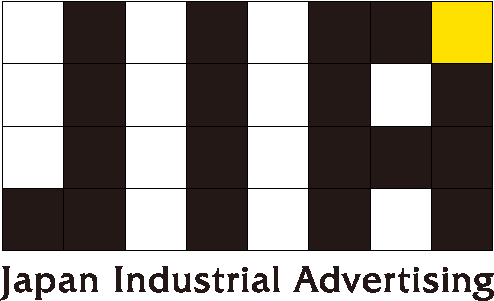本当は2人以上の子どもが欲しいにもかかわらず、その実現を躊躇する「二人目の壁」。1more Baby応援団が全国の子育て世代の約3000人に対して行った調査では、7割以上の方がこの「二人目の壁」を感じていると回答しています。
この記事では、そんな「二人目の壁」を実際に感じている方、感じたことがある方に行ったインタビューの内容をご紹介しています。もしかしたら、あなたの「二人目の壁」を乗り越えるためのヒントが見つかるかもしれません。
今回は、約1年前に体外受精で生まれた第一子をもつ、里中ショウタさん(34歳・仮名)とヒロミさん(37歳・仮名)夫婦を紹介します。エンジニアとして働くショウタさんと保健師として働くヒロミさんが、共通の趣味を通じて知り合ったのは2019年のこと。翌年に結婚後、卵管閉塞が判明したヒロミさんは、働きながら進めた不妊治療の末、第一子を産みました。
それから約1年が過ぎ、第一子は保育園に預け、ヒロミさんは職場復帰を果たしています。そうしたなか、夫婦ともに「第二子がほしい」という希望はあるものの、様々な要因から「素直に2人目を産みたいといえない」のだとか。
そこにはどのような背景や葛藤があるのでしょうか。詳しく聞いていきます。
この記事の目次
〇共通の知人を介した出会いから約1年で夫婦となり、結婚3年目から妊活をスタート
〇医師から体外受精を勧められたときの複雑な思い
〇会社を辞めて不妊治療に専念するという選択肢はなかった
〇どんどん進む不妊治療に気持ちが追いつかなかったとき、「夫の機転」に救われた
〇出産後は「頼れるものには頼る」というスタンスで子育てをした
〇「社会全体が変わっていく必要性」を感じている理由とは?
共通の知人を介した出会いから約1年で夫婦となり、結婚3年目から妊活をスタート
2人が出会ったのは、いまから約6年前の2019年。ショウタさんは30歳を目前にして、ヒロミさんは30歳を超えていたことから、お互いに〝良い人〟を探していたところ、共通の知人からの紹介を受けました。
「当時、(保健師である)自分のキャリアを考えてみても、特に結婚しなくてもいいかなと思っていました。具体的には35歳くらいまでに良い出会いがなかったら自分用のマンションを買って、そのために仕事を頑張ればいいかななんて……。一方で、子どもを産みたい、育てたいという思いもあり、良い出会いさえあれば、結婚したいなと考えていました」
そんなタイミングで、ヒロミさんはショウタさんに出会いました。第一印象は「真面目そう」。何度か食事に行くと、真面目そうな印象に加え、「きちんと話を聞いてくれる優しい人」という印象を持ちました。
「それから少しして、お付き合いすることになり、約1年の交際を経て結婚しました。割と夫も結婚願望が強かったようです」
ただ、婚姻届こそ提出したものの、コロナ禍の影響で結婚式を1年間延期させました。その影響もあり、「妊活」は結婚して3年目に入ってから始めました。しかし……。
「自分たちなりに1年近く妊活をしましたが、なかなか妊娠しなかったので、夫婦で相談し、『何か原因があるのかもしれないから病院で診てもらおう』ということになりました」
2人で病院に行き検査をしたところ、ヒロミさんの卵管閉塞が判明しました。ヒロミさんが34歳、ショウタさんが32歳のころのことです。
医師から体外受精を勧められたときの複雑な思い
「最初はタイミング法をやりました。夫のほうも検査をして、問題がなかったのですが、それでもなかなか妊娠の兆候がなかったので、卵管通水検査をしました。その検査があまりにも痛くて、迷走神経反射が起きてしまうほどだったんです。医師が言うには、『おそらく不妊の原因は卵管閉塞でしょう』とのことで、体外受精の検討を勧められました。私としては、年齢的にもあまり悠長なことは言っていられないので、体外受精をすることにしました」
タイミング法でうまくいかないときから、「なんとなく自分は人工授精や体外受精などにステップアップするのかな」と感じていたヒロミさん。医師からの体外受精の勧めに対して、「やっぱり」という思いと、「現実を突きつけられて動揺した」部分があったのだといいます。
「複雑な思いでした。夫も最初は落ち込んだ様子もありましたが、『次の方法があるんだから大丈夫だよ』と前向きなことを言ってくれたので、頑張っていこうと切り替えました」
ちなみに、ヒロミさんは前述したように保健師。一連の検査や状況がどういった意味合いを持つのか、人一倍、理解できてしまうことでの「しんどさ」もあったようです。
「学生の頃に勉強した、婦人科系の知識が蘇ってきて、まさか自分がそれに当てはまるとは……というなんともいえない感情がありましたね」
会社を辞めて不妊治療に専念するという選択肢はなかった
保健師であるヒロミさんには、「うまくいかない可能性も十分にある」という知識がありました。だからこそ、長期にわたって会社を休んだり、辞めたりして治療に専念する、という選択肢は自分にはなかったようです。
「仕事を中断し、不妊治療だけに専念した場合、キャリアの部分ではマイナスになる可能性が高いですよね。それにもかかわらず、不妊治療は成功するとは限らない。うまくいかない可能性も十分にあります。だから、仕事を中断する選択肢は自分にはありませんでした」
リモートワークが難しい保健師という職業柄、仕事を続けながら治療を続けていくのは、容易ではありません。しかし、ヒロミさんは「運が良かった」としながら、こう続けます。
「わたしが通院することにしたクリニックは、会社から電車で2駅の場所にありました。それも駅前にあったので、中抜けや時間休、午前休などを使えば、なんとかぎりぎり通うことができました」
さらに、ピーク時は2日に1回くらい通院が必要だったため、仕事上でかかわる医師や上司などには、自分の状況を包み隠さずに伝えていたといいます。
「不妊治療をしていることだけでなく、『こういう治療をします』と具体的に伝えていました。想像以上に通院することが多かったのですが、先生(医師)や上司など、職場のみなさんはものすごく配慮してくれたと思います」
いちど、上司の上司にあたる女性部長と面談したときには、こんなやりとりもあったのだとか。
「保健師として、社員の方々との面談があったりするのですが、リスケ(日程調整)が続いたことがありました。『申し訳ないな』と思って、部長とのミーティングのときにその話をしたら、『それはお互いさま。もし子どもが生まれたら、そんなことは山ほどでてくるし、逆に不妊治療や子育てをしている社員さん、あるいは熱が出た社員さんから、リスケをお願いされたら、どう? 全然、気にしなくていいですよと答えるでしょう? だからあまり気にする必要はない』と言ってくださって、ちょっとだけ肩の荷がおりたことがありました」

どんどん進む不妊治療に気持ちが追いつかなかったとき、「夫の機転」に救われた
幸いにも、体外受精におけるハードルの1つである採卵は、一度目で6つが採れました。そのうち受精卵として3つを凍結保存し、もっともグレードのよいものを移植することになりましたが……。
「担当の先生が、『最もグレードが良いこれを使って移植しましょう。このあとは、こんな流れで進めていきます』と、どんどん前に進めていくので、わたしとしては気持ちが追いついていかなくて、〝混乱したまま、先生が言うままに事が進んでいく〟という感覚に陥っていました」
このとき同席していたショウタさんは、ヒロミさんの様子に気がつき、「それって、先生の提案のとおりにやらないといけないということでしょうか? できれば、少し気持ちを落ち着かせてから進めるというのでは、駄目なんでしょうか?」と言ってくれたそうです。
「夫が話を遮ってくれた結果、先生からは『移植をしたくなってから進める形で大丈夫ですよ』と返ってきたので、2〜3ヶ月ほど間を空けることにしました。理由としては、気持ちを落ち着かせてからということが第一で、あとはコロナ禍で顔を見せられていなかった遠方に住む祖父母のところに行ったり、親戚の結婚式に参加したりといったこともしました」
その後、移植を行い、数週間後には胎嚢も確認でき、無事に着床していることがわかりました。ただ、安定期までは余談を許さないということで、「過度な期待はしないようにした」といいます。
「5週目くらいで、『そろそろ(産むための)病院を探しましょう。母子手帳も持ってきてください』と言われて、喜びと実感がわいてきました。夫もわたしと同じで、最初はそこまで喜びを表現していませんでしたね。そこは、わたしに気を遣っている部分もあったかと思います」
実は、ショウタさんが〝気を遣っている〟ということをヒロミさんは何度か感じたことがあるようです。
「結婚の前後あたりでは、『やっぱり子どもが欲しいな』ということを言っていました。でも、実際に不妊治療を始めだして、体外受精になりそうとなったときには、『無理はしなくていいよ。2人だけの生活でもいいよ』と言ってくれたりしたこともあったので、彼なりに過度なプレッシャーをわたしに与えないよう、気を配ってきたのだと思います」
出産後は「頼れるものには頼る」というスタンスで子育てをした
妊娠後は、食べづわりが少し長めに続いたものの、基本的に経過は順調。家事などショウタさんの積極的なサポートに加え、有給休暇を使った長めの産休も取得できたこともあり、大きなトラブルもなく無事に出産することができました。
夫婦ともに実家が遠方ということもあり、出産のあとは産後ケア施設を利用しました。
「実家は遠いし、実父も仕事をしていたので、里帰り出産はしませんでした。そのかわり、コロナ禍で新婚旅行も行けなかったということもあったので、産後ケア施設で贅沢をさせてもらいました。本当に、快適でしたね。産後の回復も早かったように感じます」
ショウタさんのほうも、1週間ほど休暇を取ったり、上司と相談のうえ在宅勤務を積極的に活用したりして、なるべく一緒に過ごす時間を増やそうとしてくれたのだとか。さらに行政主導のヘルパーサービスも活用したようです。
「生後2ヶ月くらいのときだったのですが、メンタルバランスの不調を感じたので、行政を通じてマッチングした産後ヘルパーさんにきてもらって、ご飯をつくってもらったり、家事をしてもらったり、相談に乗ってもらったりしました。補助金も使えたので、経済的な負担もなかったです」
出産からおよそ1年の休暇を経て、ヒロミさんは職場復帰をしました。子どもは保育園に預け、在宅勤務もうまく組み合わせながら、仕事の量を少しずつ増やしていっているといいます。
「自分でも不思議だなと思うんですけど、子育てだけに注力する選択肢ももちろんありました。でも、なぜか出産する前から、わたしは子育てはいつか終わるし、そのときに自分になにが残っているのかなと考えたときに、せっかく今までやってきた仕事を途切れさせてしまうのは、もったいないと感じたんです」
もしかしたら、今までと同じ仕事の量はこなせないかもしれない。けれど、細く長く続けていく道もあるのではないか……そんなふうに考えているのだとヒロミさんはいいます。
「もちろん、会社には出産前からたくさん配慮してもらってきたので、〝お互いさま〟じゃないけれど、少しは還元できたらという思いもあります。あとは、いまは出産前に働いていた現場を離れて、管理部門のほうでの勤務になっているのですが、保健師という職業柄、キャリアを積んでいくには何かしらの武器を持っている必要があると思っているので、自分の武器を少しでも増やせたらという願望もあったりはします」
「社会全体が変わっていく必要性」を感じている理由とは?
そうしたなか、ヒロミさんは2人目にチャレンジするかどうか決めかねているといいます。
「2人目は欲しいです。でも、躊躇してしまう自分がいるのも確かです。1人目を育てながら、2人目の不妊治療に臨むとなったら、せっかくいただいた今の仕事を放りだす必要が出てくるのではないかと思っているからです。通院には時間だけでなく、費用もかかります。夫のキャリアも尊重したいので、彼の長時間労働を無理やり短くさせるのは本望ではありません。頼れる親族も近くにいません。そうなると、自分が時短をするほかないのですが、自分のキャリアを考えると、あまり時短勤務ばかりしていたくもない。年齢的なリミットもあるなか、2人目をどうするかは棚上げ状態になっています」
そうしたヒロミさんを見かねたショウタさんが、「時短勤務をする」という提案をしてきたこともあったのだとか。
「彼はそういう考えを持っているみたいです。でも、正直なところ会社自体の文化として、言い出しにくいのが本音のようです。評価にも響くのではないかという〝見えない壁〟のようなものがあって、時短勤務をしてもいいという気持ちはありつつ、実際にはできないというのが実情で、そんな板挟みの人は、けっこう多いように思います。実際、私も復帰してみて、時短勤務は女性しかいないということに気がつきましたから」
だからこそヒロミさんは、「社会のほうが変わっていかなければ、自分たちのような子育て世代の悩みは解決できないのではないか」という思いがあり、今回のインタビューに応じてくださったのだと話します。
「子どもを1人にするにしても、2人にするにしても、あるいは介護や療養期間を取るにしても、敷居が低くなる世の中になるといいなと思っています。どうしても個人や家族の中での問題としがちですが、個人や家族の努力だけでは乗り越えられないものがあります。だからこそ、それは女性の働き方だけでなく、男性の働き方も含めて、もっと柔軟に働けるようになって、社会全体で子育てやケアをしていける世の中になってほしいなって思うんです」
いかがでしたでしょうか。出産や育児にかかわる国の制度は少しずつ変わってきており、男性の育児休暇の取得や時短勤務も増えてきたと言われています。しかし実際には、様々な見えないハードルがあり、まだまだ改善の余地があるように感じるお話ではなかったでしょうか。
最後になりましたが、インタビューに応じてくださりありがとうございました。