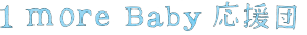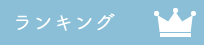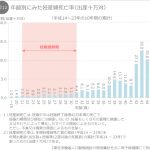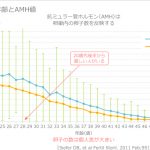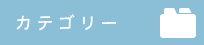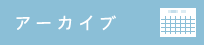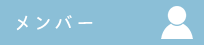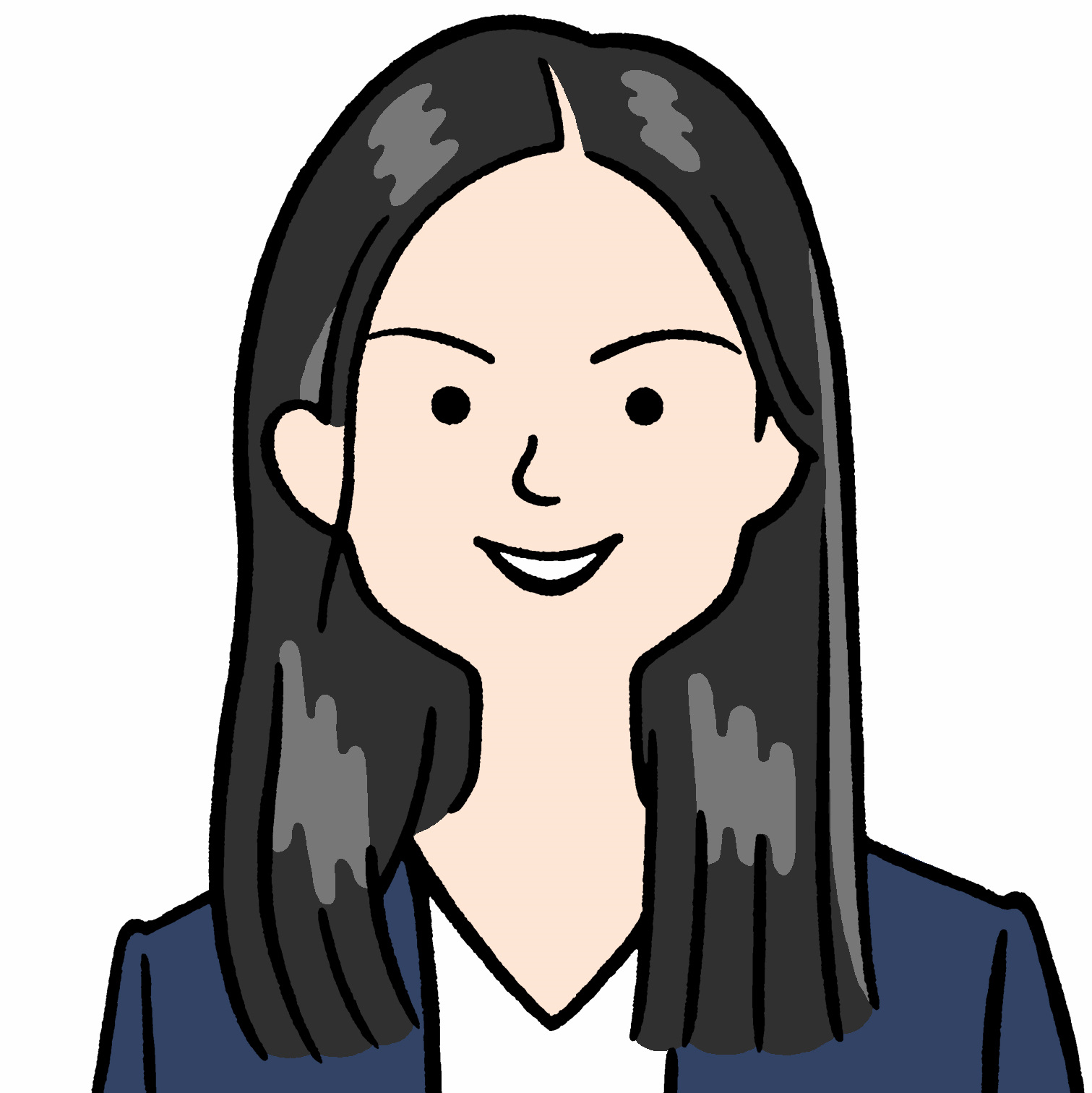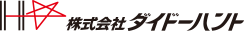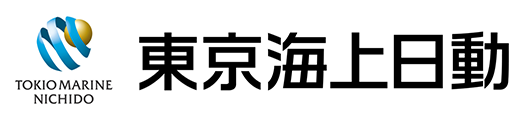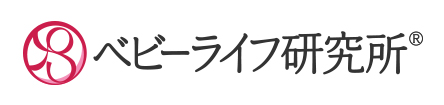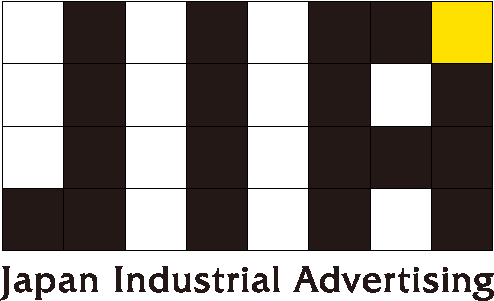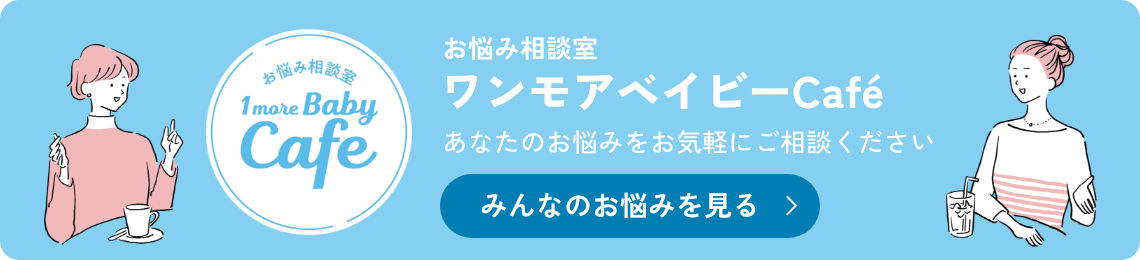
-
妊娠できる?できない?『早発卵巣不全』の原因と治療について

専門家記事
2024年10月21日
もっと見る日本人女性の閉経の平均年齢は約51歳と言われていますが、個人差が大きく、早い人では40歳台前半、遅い人では50歳台後半に・・・ -
【私が経験した二人目の壁】残っていた受精卵に揺れる気持ち。どうしても書けなかった破棄書類……夫婦がくだした決断は?

秋山 開
2024年10月04日
もっと見る本当は2人以上の子どもが欲しいにもかかわらず、その実現を躊躇する「二人目の壁」。1more Baby応援団が全国の子育て・・・ -
出産は長寿の秘訣?分娩回数と女性の長期的死亡リスクとの関係

齊藤英和
2024年09月26日
もっと見る今回のコラムでは、出産回数と、「女性の全原因による長期的死亡リスク」や「特定の原因による長期的死亡リスク」との関連性につ・・・ -
妊娠中の方、必読!妊娠中や産後のうつ病リスクを軽減させる『食事』と『ビタミンD』

齊藤英和
2024年08月26日
もっと見る今回は、妊娠中や産後のうつ病のリスクを軽減するために必要な食事とビタミンDについてお話したいと思いますが、ビタミンDに関・・・ -
【私が経験した二人目の壁】『感覚過敏』の第一子の子育てと『経済的な理由』から第二子を躊躇していた夫婦のリアルな気持ち

秋山 開
2024年08月08日
もっと見る本当は2人以上の子どもが欲しいにもかかわらず、その実現を躊躇する「二人目の壁」。1more Baby応援団が全国の子育て・・・