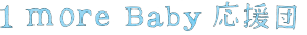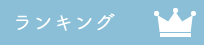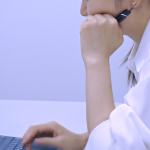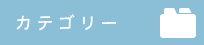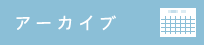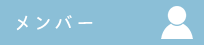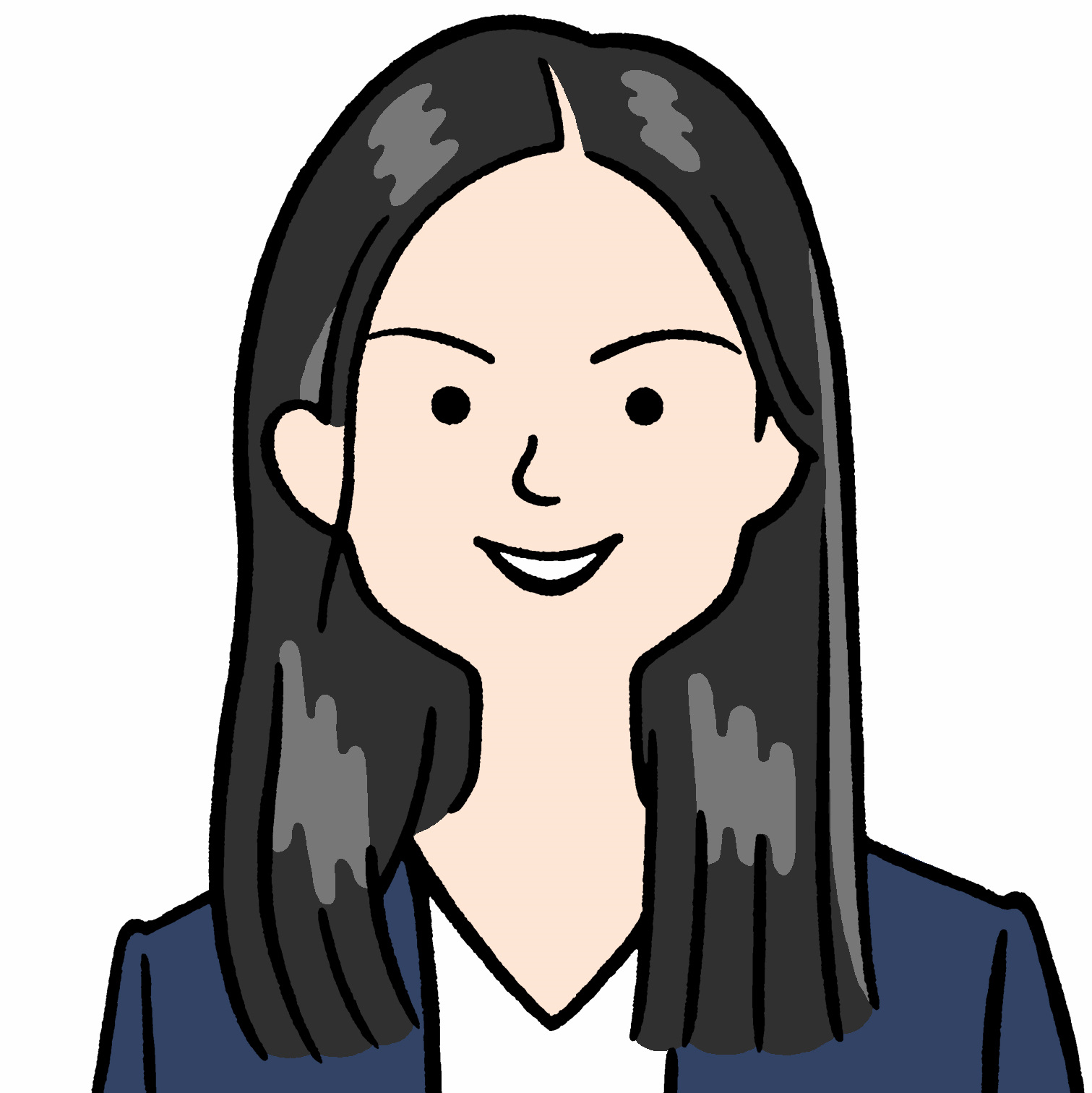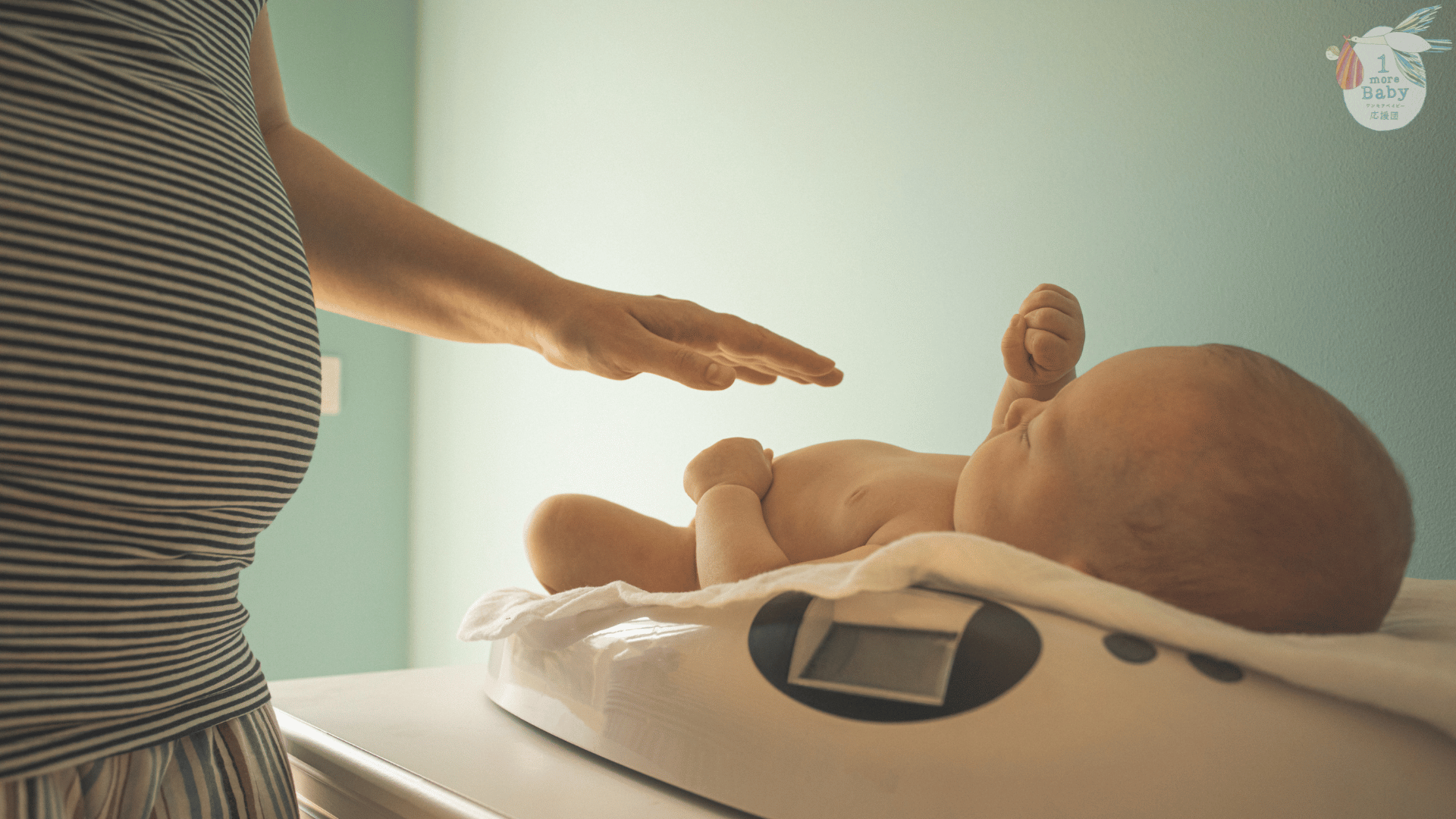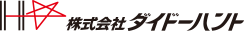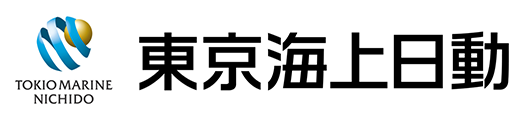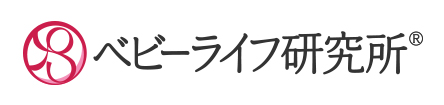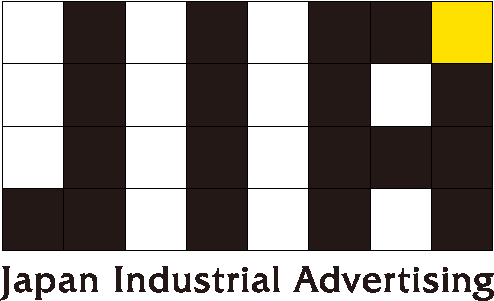「口は万病の元」という言葉を聞いたことがありますか? 不妊症も例外ではないのかもしれません。
不妊症の原因の1つである反復着床不全と口腔内の不健康に、関連性があることを示唆する研究結果が、山梨大学と医療法人渓仁会による研究グループによって2024年8月7日版のスイスのジャーナル誌『Journal of Clinical Medicine』に発表されたのです。
では、具体的にどういった関連性があるのでしょうか。
山梨大学大学院総合研究部医学域の小野洋輔臨床助教と吉野修教授、そして医療法人渓仁会手稲渓仁会病院不育症センターの山田秀人センター長らによる研究グループは、体外受精などの高度な不妊治療を施しても、なかなか妊娠に至らない重度の不妊症といえる反復着床不全の人のなかで、子宮内膜症を併発している人には、子宮内膜に歯周病の原因菌として知られるディアリスター菌が高頻度(約11倍)で検出されたとしています。

端的にいえば、口のなかが不健康な状態だと、不妊症につながる子宮内膜症を引き起こす可能性があるかもしれないということです。
そこで今回は、同研究グループのメンバーである小野洋輔臨床助教(以下、小野先生)に、同研究やその結果が不妊に悩む方にもたらす影響や、新たな不妊治療や検査への展開などについて聞いていきます。
この記事の目次
〇「無菌」と言われることもあった子宮内膜の菌種が〝科学の発達〟で明らかになってきた
〇早産との関連性も指摘されるディアリスター菌の保有率が高いことが判明
〇子宮内細菌叢検査が、新たな不妊検査の選択肢に?
〇不妊患者においても口腔ケアを行うことに〝損〟はない
「無菌」と言われることもあった子宮内膜の菌種が〝科学の発達〟で明らかになってきた
これまでのわたしたち1moreBaby応援団が行ってきた不妊に悩む方々へのインタビュー記事などからもわかるように、「不妊症」にはさまざまな原因があります。もっといえば、「絶対にこれが原因(要因)である」という明確なことがわかるケースはほとんどありません。それは妊娠できた場合でも、できなかった場合でも同様です。
そうしたなか、妊娠の確率を高めるための不妊症に対する治療法の確立が、様々な研究者や機関において模索されており、小野先生らのグループも例外ではありません。
では、同グループはどのような研究を行ったことで、「口のなかの状態が不妊症に影響を与える可能性がある」ということに至ったのでしょうか。小野先生は言います。
「子宮内膜症が不妊につながることはよく知られています。ただ、そのメカニズムは十分にはわかっていません。近年、腸内の細菌叢が子宮内膜症の発症に関係している可能性が報告されています。また、子宮の中にも細菌が存在し、これらが受精卵の着床や妊娠の成立に関わっているかもしれないことも注目されています。そこで私たちは、不妊を呈する子宮内膜症患者の子宮内にどういった細菌(子宮内細菌叢)がいるのかを詳しく調べてみることにしました。具体的には同じような難治性の反復着床不全とされる患者さんたちのうち、子宮内膜症がある人とない人を比べて、菌の数や種類においてどのような違いがあるのかを見ていくことにしたのです」
子宮内膜の細菌叢(さいきんそう=特定の部位に存在する細菌の集合体)を調べる古典的な方法は、細菌培養同定法(培養法)というもの。綿棒のようなもので子宮内膜を拭い取り、培地で菌が生えてくるかどうかを調べる方法です。しかし、この方法はあまり精度が高くありません。
「かつて子宮内膜は無菌だと主張する人もいたほどで、菌の数はそんなに多くありません。だから、培養法ではあまりうまく判断できませんでした。しかし、この10〜20年で、科学の発展にともない医療技術が進歩し、次世代シークエンサーを用いた遺伝子(DNA)検査で、細菌叢を詳細に見ていくことが可能になったのです」
早産との関連性も指摘されるディアリスター菌の保有率が高いことが判明
研究の結果、子宮内膜には、様々な種が存在していることがわかりました。そのなかでも、これまでの研究・論文などから不妊症との関連が示唆されている菌について以下の表1にまとめられています。
 出典:山梨大学プレスリリース「子宮内膜症を合併する反復着床不全患者の子宮内膜に歯周病菌のディアリスター菌を高頻度に検出」より
出典:山梨大学プレスリリース「子宮内膜症を合併する反復着床不全患者の子宮内膜に歯周病菌のディアリスター菌を高頻度に検出」より
今回の研究では、対象となった患者さんの数が43名と多くないため、「一般化できるほどの数字ではない」と前置きしたうえで、小野先生はこのように解説します。
「いわゆる乳酸桿菌、子宮のなかの善玉菌とされるものであるラクトバチルス菌は、子宮内膜症がある患者群とない患者群に差はありませんでした。一方で、子宮内膜症のある方では、子宮内膜に存在する細菌の種類が多く、通常優勢であるラクトバチルス以外の細菌も多く検出される傾向がありました。このことから、細菌叢(マイクロバイオーム)のバランスが乱れている可能性が考えられました。
中でも注目されたのが、嫌気性菌であるディアリスター菌です。子宮内膜症を合併している場合には、この菌の検出率が約11倍高く、さらにディアリスター菌を持つ患者さんでは、検出される細菌の種類も多い傾向がみられました。こうしたことから、ディアリスター菌のなどの嫌気性菌の存在が、子宮内の細菌バランスの乱れ(dysbiosis)や不妊症のメカニズムに何らかの関連を持つ可能性があり、今後のさらなる研究が期待されます。」 このディアリスター菌は口腔内や腸のなかにいて、歯周病の原因菌となることも知られ、早産との関連性が指摘されることもあります。その働きは十分に明らかにされているわけではないと小野先生は指摘しつつも、「子宮内膜にディアリスター菌がいるということは、子宮の中が何らかの炎症状態にあることを示している可能性がある」と話します。
「高い炎症状態にあれば、着床不全を起こすリスクが高まり、着床が不十分になると、その後の胎盤の成長にも影響が出たり、早産につながったりすることが予想されます。このディアリスター菌がどのようにして、子宮内に至ったのかは不明ですが、口のなかにいるディアリスター菌が血液などを通って子宮にまわってきている可能性も否定はできません」 つまり、もしも口腔内の菌が子宮に移動することがあるとするならば、将来的にしっかりと歯磨きをしたり、口腔ケアをしたりすることが、着床不全の改善に役立つかもしれないのです。
「そもそも、そうした口腔内の環境を整えることは、妊娠だけに限らず、体の健康にとって良いことですので、(厚生労働省やWHOも推奨している)プレコンセプションケアの一環として、歯を磨いたり、口腔内を整えたりすることを提唱しても悪いことではないのかなと思います」
子宮内細菌叢検査が、新たな不妊検査の選択肢に?
また、近年は妊活に際して、ERA検査(着床に最適なタイミングを調べる検査)やEMMA検査(子宮内膜の細菌バランスを調べる検査)、ALICE検査(慢性子宮内膜症の関連する10種類の病原菌の有無を調べる検査)が広まってきています。子宮内膜細菌叢検査は、より広い範囲で子宮内膜に存在する細菌全体の特徴(多様性や特定の菌の存在など)を調べることができるため、今後、本研究に関連するデータがさらに蓄積されれば、着床不全の検査として重要な意味をもってくるかもしれないと小野先生は続けます。
「仮に、ディアリスター菌などの嫌気性菌が着床の邪魔をしているとするのであれば、たとえば子宮内膜症があってもなくても、着床不全の患者さんの子宮内の細菌叢を調べたときにディアリスター菌などの嫌気性菌がいれば、抗生物質や乳酸菌剤を飲んでもらい、それでディアリスター菌が消えたのちに、着床を試みてもらう。その結果、妊娠できたというデータが蓄積されていったら、これまでとは異なる検査方法やそれに対する治療法というのが出てくるのかなと思います。
ただし、現段階では、子宮の中にディアリスター菌のような嫌気性菌がなぜいるのか、どのようなふるまいをするか、実際に不妊症の原因となるのかに関しては、不明です。このことを今後調べることが、子宮内膜細菌叢検査の意義や不妊症に対する新しい治療戦略を生み出すカギになると考えられます。」
とはいえ、現段階で伝えられるメッセージとしては、ディアリスター菌だけに絞った治療をするのではなく、「子宮のなかを良い環境に整えることが大事」ということだといいます。
「(ディアリスター菌やレンサ球菌のような)嫌な菌がいることは、子宮内が炎症状態である1つの目安になるかもしれませんが、それよりも重要なことは、子宮のなかをラクトバチルス、乳酸菌などが多い状態にして、妊娠を目指すということです。」
また、今回の調査で、早産や産褥子宮内膜炎や、新生児感染症の原因菌となることが知られているレンサ球菌も、子宮内膜症をもつ患者群の保有率のほうが3.6倍ほど高かったこともわかっています。このことも、子宮内環境が高い炎症状態にあることを示してい可能性があるということです。
不妊患者においても口腔ケアを行うことに〝損〟はない
小野先生はこう続けます。
「ディアリスター菌やレンサ球菌などの存在が、子宮内が炎症状態であることを反映しているのみならず、不妊症に関与することが明らかとなれば、これらの細菌を保有する反復着床不全の患者さんにおいては、胚移植の前に抗菌薬やプレ・プロバイオティックスの治療などで子宮内細菌叢のバランスを整える必要がでてくるかもしれません。」
さらに、これから妊活をしようとしている人や、漠然と不妊に対して不安をもっている人にも、こうアドバイスします。
「今回の研究からわかったことは、子宮内膜症を有する不妊患者で、通常は口腔内に多いディアリスター菌な嫌気性菌の検出率が高かったということです。これらの菌の存在が、子宮内環境や着床にどのような影響を及ぼすかはまだ不明ですが、今後の研究により関連性が明らかになる可能性があります。現段階で推奨される治療ステップとしては、まずは一般的な不妊治療を受けることです。子宮内膜症という診断結果があるなら、その治療もセットで行っていくことが必要です。繰り返し標準的な不妊治療をうけてもうまくいかないときには、今後、子宮内の細菌叢も調べみることも1つの選択肢となるかもしれません。子宮のなかの環境を調べるというのは、不妊研究において興味深いテーマであると思いますので、今後も様々な研究が進んでいくと思います」
まだまだわかっていないことも多いものの、本研究によって、不妊症と歯周病菌の一種であるディアリスター菌との関連が示唆されました。将来的には、妊娠率の向上につながる新たな不妊治療や検査法の確立が期待されます。
また、不妊に悩む方や、これから妊活を始めようと考えている方にとっても、口腔ケアに気を配ることは決して無駄ではないといえるでしょう。
こうした背景を踏まえると、妊娠を希望する方が日頃から口腔内を清潔に保ち、全身の健康を整えておくことは、プレコンセプションケア(妊娠前の健康管理)の一環として、有意義な取り組みになる可能性があります。しばらく歯科検診を受けていない方は、妊活を始めるタイミングで一度受診し、日常的な歯磨きや口腔ケアへの意識を高めてはいかがでしょうか。